Subscribe
登録者情報
ご登録ありがとうございます。
下記のフォームを入力ください。
最新号ニュースレター
#59 July 27, 2024
パリの日本文化会館で、KENZO TANGE – KENGO KUMA Architectes des Jeux de Tokyoという展覧会が開催された。(2024.5.2 – 6.29)僕がそもそも建築家を志すきっかけとなったのが、1964年の第一回の東京オリンピックの時、父に連れられて見に行った丹下先生設計の代々木競技場である。
僕は10才で、ネコ好きで獣医さんになるのを夢見る内気な少年だった。当時の東京は、木造住宅が建てこむ、低層のつつましい都市で、その中に屹立する丹下先生のコンクリートの塔、そこからケーブルで吊られたピカピカに輝く金属屋根に衝撃を受けた。まさか、その僕が半世紀後の第二回目の東京オリンピックのスタジアムの設計に携わるなど夢にも見ることさえありえなかったし、その雲の上の憧れの人、丹下先生との二人展をパリで開くなどということは、想像の限界をはるかに超えていた。
ただ展覧会会場を一人でじっくりと歩きまわって、丹下先生という巨大なベンチマークがあったからこそ、自分のやるべきことが見つかり、自分の位置をポジショニングできたのだということを、はっきりと確認することができた。それに気付くと、あらためて感謝の気持ちが心の底から湧いてきて、先生の写真の前で、手をあわせた。
その自分の位置とは、一言でいえば、丹下先生の垂直性に対して、自分は水平ということであり、丹下先生のコンクリートに対して、自分は木でいこうということである。
高度成長の日本は、コンクリートで大きな建築をどんどん大量に作る必要があった。一方、少子高齢化の人口減少の日本は、昔からなじみ深い材料である裏山の木を使って、小さな建築を、少しずつ作ればいいというのが、僕のたどり着いた小さな結論である。この展覧会とカタログのグラフィックデザインをお願いした原研哉さんは、展示もブックレットも絶対にモノクロがいいと提案してくださった。モノクロにして情報量を少なくすることによって、それぞれの時代の雑音が消えていくだろうという意見だった。
丹下先生の作品の撮影は、丹下先生が「桂離宮(1960)」の本を一緒に作った、モダニズムフォトの代表的写真家である石元泰博。僕の作品は、現代を代表する写真家の一人で、特にそのモノクロのすさまじいミニマリズムに僕が惚れ込んでいる瀧本幹也さんにお願いした。それぞれの時代を代表する二人の写真家の作品の前を歩いていくと、ある不思議な感情が沸き起こってきた。
二つの時代は確かに対極的であり、逆を向いている。しかし、それ以上に二人の写真家によるモノプロのプリント群は、どれも同じような空気感を有していて、とても近しいものに感じられてきたのである。
その親近性はどこから来るのだろうか。そもそも丹下先生の代々木に憧れて建築家になったくらいだから、僕の血液の中には、対極をめざして乗り越えようなどとは思ってみたものの、丹下的なる成分がたっぷり含まれているということが考えられるかもしれない。
あるいは、われわれ二人は共に日本という場所に生まれ、育って、どうあがいてもそこから抜け出せないということも、あるのかもしれない。日本からだいぶ離れたパリという場所にいたから、余計にそう思えたということもあるだろう。あるいは、成長と衰弱という対極を向いているように当人が感じている50年を隔てた二つの時代が、人類の数10万年の歴史の中では、本人が思っているほどには対極でも対照でもないのかもしれない。結局、アーキテクトは建築という長持ちするものを作りながら、きわめて近視眼的なのかもしれない。
そんなことを考えながら、そのモノトーンに埋め尽くされた静かな会場を、なるべくゆっくりと、大またで歩いてみた。日々の近視眼的な焦り、悩みに追われ続けている自分から、少しでも抜け出し、数10万年という大きな時間の中で歩き、考えたいと思ったのである。
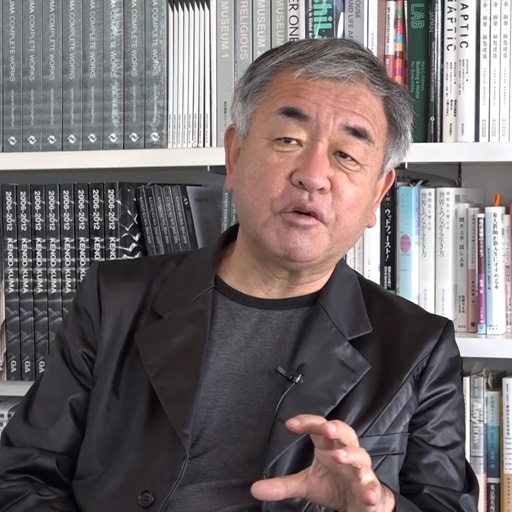
ProjectsStone Grove
 This project, Stone Grove, utilizes a unique stone composite material to create a formally natural and spatially wild installation. The project utilizes principles of contemporary Ikebana, which embraces the use of alternative materials to practice this storied art-form. This contemporary interpretation of Ikebana evinces that arrangements can be crafted anytime, anywhere, and in collaborative conversation with craftspeople. An immersive environment that embraces architectural scale manifests itself through the careful, intentional placement of each component based on this cultural compositional technique. The installation consists of stone modules which are carefully joined to create individual, aesthetically and structurally balanced compositions. These are then arranged within a free field, wherein the maximum and minimum extensions possible with the material are expressed by the seemingly randomized lengths of each panel. As one moves around the project, the field oscillates between the gestural, the random, and the natural, constantly changing based on one’s perspective. From certain views, one can see all the way through the installation, while at other vantages the modules merge to create the feeling of a dense thicket. The stone product, manufactured by Quarella, is a composite material composed of various-sized granules that are blended with natural pigments and resins to create … Read More
This project, Stone Grove, utilizes a unique stone composite material to create a formally natural and spatially wild installation. The project utilizes principles of contemporary Ikebana, which embraces the use of alternative materials to practice this storied art-form. This contemporary interpretation of Ikebana evinces that arrangements can be crafted anytime, anywhere, and in collaborative conversation with craftspeople. An immersive environment that embraces architectural scale manifests itself through the careful, intentional placement of each component based on this cultural compositional technique. The installation consists of stone modules which are carefully joined to create individual, aesthetically and structurally balanced compositions. These are then arranged within a free field, wherein the maximum and minimum extensions possible with the material are expressed by the seemingly randomized lengths of each panel. As one moves around the project, the field oscillates between the gestural, the random, and the natural, constantly changing based on one’s perspective. From certain views, one can see all the way through the installation, while at other vantages the modules merge to create the feeling of a dense thicket. The stone product, manufactured by Quarella, is a composite material composed of various-sized granules that are blended with natural pigments and resins to create … Read MoreProjects鹿田室礼 籐家具
 籐(ラタン)家具は、その軽さや曲げ加工の容易さが特徴であるが、その特徴にさらに踏み込んで、「ひとふでがき」のような一本の線デザインで家具全体を統制することを試みた。 線をねじりながらつなげ、細かい切れ込みを入れた籐を従来よりも鋭角に曲げ、座面の端部の籐のファブリックを下地を巻き込んでテーパーエッジではり込めた。それらの新しい技術、ディテールが、籐に新しい可能性を与えた。 メインフレームである籐は、インドネシアで採取したマナウ籐を使用し、太いものはフレームに、細いものは座面としてウィッカー編みや網代編みにし、素材の全てを使い切って、環境に対しても配慮した。 Read More
籐(ラタン)家具は、その軽さや曲げ加工の容易さが特徴であるが、その特徴にさらに踏み込んで、「ひとふでがき」のような一本の線デザインで家具全体を統制することを試みた。 線をねじりながらつなげ、細かい切れ込みを入れた籐を従来よりも鋭角に曲げ、座面の端部の籐のファブリックを下地を巻き込んでテーパーエッジではり込めた。それらの新しい技術、ディテールが、籐に新しい可能性を与えた。 メインフレームである籐は、インドネシアで採取したマナウ籐を使用し、太いものはフレームに、細いものは座面としてウィッカー編みや網代編みにし、素材の全てを使い切って、環境に対しても配慮した。 Read More